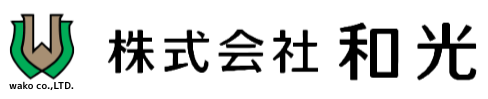通話料無料 9:00~17:30
0120‐66‐4114
永代供養料の封筒の書き方完全ガイド|表書きから渡し方まで徹底解説
投稿日:2025年9月27日

目次
- 封筒の選び方と準備
- 使用する封筒について
- 封筒の表書きの書き方
- 基本的な表書きの文言
- 施主名の記載方法
- 文字の配置
- 封筒の裏書きと金額の書き方
- 中袋がある場合
- 中袋がない場合
- 金額の旧漢字表記例
- 永代供養料の渡し方とマナー
- 封筒の包み方
- 渡すタイミング
- 渡し方の手順
- 費用相場と注意点
- 永代供養料の相場
- お布施の相場
- 支払い方法について
- 永代供養料とお布施の違い
- 永代供養料
- お布施
- よくある質問(FAQ)
- Q: 封筒の表書きは「御布施」と「永代供養料」どちらがいい?
- Q: 封筒に使う筆記具は何でもいい?
- Q: お札は新札と旧札どちらを使えばいい?
- Q: 書き損じた場合はどうすればいい?
- Q: 銀行振込を指定されている場合は?
- Q: のし袋は使用できますか?
- Q: 表書きの文字が小さすぎたり大きすぎたりしないか心配です
- まとめ
永代供養を依頼する際、「封筒に何を書けば良いのか」「どのようなマナーで渡すべきか」と不安に感じる方は少なくありません。この記事では、永代供養料やお布施を納める際の封筒の正しい書き方から渡し方まで、初心者の方でも失礼のないよう準備できるポイントを詳しく解説します。
封筒の選び方と準備
使用する封筒について
永代供養料を納める際は、白無地の封筒を使用します。郵便番号枠や装飾のない、シンプルな白い封筒を選ぶことが大切です。
選ぶべき封筒の特徴
白無地(郵便番号枠なし)
過度な装飾がないもの
適度な厚みがあるもの
過度な装飾がないもの
適度な厚みがあるもの
必要な筆記具
文字を書く際は以下を準備しましょう:
濃い墨または黒い筆ペン
薄墨は使用しません(弔事とは異なるため)
字が苦手な方も筆ペンで十分です
濃い墨または黒い筆ペン
薄墨は使用しません(弔事とは異なるため)
字が苦手な方も筆ペンで十分です
新札・旧札について
永代供養料のお布施では新札を使用しても問題ありません。むしろ、できるだけ綺麗なお札を包むことがマナーとされています。折り目の少ない、状態の良いお札を用意しましょう。
封筒の表書きの書き方
基本的な表書きの文言
封筒の表面には縦書きで以下のいずれかを記載します:
一般的な表書き
御布施(お布施)
永代供養料
永代供養料
浄土真宗の場合
永代経懇志
施主名の記載方法
表書きの下段には施主(喪主)の名前を書きます
個人名:「田中太郎」など氏名を記載
家名:「田中家」など姓に「家」をつけて記載
個人名:「田中太郎」など氏名を記載
家名:「田中家」など姓に「家」をつけて記載
文字の配置
縦書きで記載
中央寄せで配置
文字の大きさは封筒に対してバランスよく
中央寄せで配置
文字の大きさは封筒に対してバランスよく
封筒の裏書きと金額の書き方
中袋がある場合
中袋の表面:
金額を旧漢字で記載
例:20万円 → 「金弐拾萬圓也」
中袋の裏面:
住所
氏名
金額を旧漢字で記載
例:20万円 → 「金弐拾萬圓也」
中袋の裏面:
住所
氏名
中袋がない場合
封筒の裏面に以下を記載します:
住所
氏名
金額(旧漢字表記)
住所
氏名
金額(旧漢字表記)
金額の旧漢字表記例
| 算用数字 | 旧漢字表記 |
|---|---|
| 1万円 | 金壱萬圓也 |
| 3万円 | 金参萬圓也 |
| 5万円 | 金伍萬圓也 |
| 10万円 | 金拾萬圓也 |
| 20万円 | 金弐拾萬圓也 |
| 30万円 | 金参拾萬圓也 |
旧漢字を使用する理由は、後から数字を改ざんされないようにするためです。
永代供養料の渡し方とマナー
封筒の包み方
袱紗(ふくさ)に包む
紫や紺、グレーなどの落ち着いた色を選ぶ
封筒を袱紗の中央に置き、左→上→下→右の順に包む
切手盆に載せる
小さな盆(切手盆)に袱紗ごと載せる
直接手で渡さないのがマナー
紫や紺、グレーなどの落ち着いた色を選ぶ
封筒を袱紗の中央に置き、左→上→下→右の順に包む
切手盆に載せる
小さな盆(切手盆)に袱紗ごと載せる
直接手で渡さないのがマナー
渡すタイミング
法要の後が一般的
僧侶にお時間をいただけるタイミングで
「本日はありがとうございました」などの挨拶とともに
僧侶にお時間をいただけるタイミングで
「本日はありがとうございました」などの挨拶とともに
渡し方の手順
袱紗から封筒を取り出す
封筒の表書きが相手から読めるよう向きを整える
両手で丁寧にお渡しする
「心ばかりですが」「お納めください」などの言葉を添える
封筒の表書きが相手から読めるよう向きを整える
両手で丁寧にお渡しする
「心ばかりですが」「お納めください」などの言葉を添える
費用相場と注意点
永代供養料の相場
永代供養料は供養の形態によって異なります
供養形態別の相場:
個別墓(一定期間後合祀):50万円~150万円
集合墓:20万円~60万円
合祀墓:10万円~30万円
供養形態別の相場:
個別墓(一定期間後合祀):50万円~150万円
集合墓:20万円~60万円
合祀墓:10万円~30万円
お布施の相場
納骨法要の際のお布施相場:
一般的な相場:3万円~5万円
地域や寺院による差があるため事前確認が重要
一般的な相場:3万円~5万円
地域や寺院による差があるため事前確認が重要
支払い方法について
手渡しが基本
銀行振込を指定される場合もある
事前に寺院・霊園に確認しておく
銀行振込を指定される場合もある
事前に寺院・霊園に確認しておく
永代供養料とお布施の違い
永代供養料
永代にわたる供養を依頼するための契約料
供養の代行を寺院に依頼する費用
一度支払えば基本的に追加費用なし
供養の代行を寺院に依頼する費用
一度支払えば基本的に追加費用なし
お布施
法要を行っていただく僧侶への謝礼
読経や法話への感謝の気持ち
年忌法要の度に必要となる場合が多い
同時に納める場合は、封筒を分けて「永代供養料」「御布施」と表書きを使い分けるか、まとめて「御布施」として納めることもできます。
読経や法話への感謝の気持ち
年忌法要の度に必要となる場合が多い
同時に納める場合は、封筒を分けて「永代供養料」「御布施」と表書きを使い分けるか、まとめて「御布施」として納めることもできます。
よくある質問(FAQ)
Q: 封筒の表書きは「御布施」と「永代供養料」どちらがいい?
A: 基本的にはどちらでも構いませんが、目的を明確にしたい場合は「永代供養料」と書きます。浄土真宗では「永代経懇志」を使用します。別々に納める場合は、それぞれの目的に応じて書き分けましょう。
Q: 封筒に使う筆記具は何でもいい?
A: 太字の筆ペンや墨を使い、濃い墨で書くのがマナーです。薄墨は弔事で使用するものなので、永代供養では使いません。字が苦手な方でも筆ペンで丁寧に書けば問題ありません。
Q: お札は新札と旧札どちらを使えばいい?
A: 永代供養のお布施では新札を使用しても問題ありません。むしろ、できるだけ綺麗で折り目の少ないお札を包むのがマナーとされています。
Q: 書き損じた場合はどうすればいい?
A: 修正液や修正テープは使用せず、新しい封筒に書き直しましょう。不安な場合は、事前に練習用の紙で文字のバランスを確認してから本番の封筒に書くことをおすすめします。
Q: 銀行振込を指定されている場合は?
A: 事前に寺院・霊園に確認し、振込指定があれば銀行振込で構いません。その場合も、振込明細を持参し、法要の際に「振込させていただきました」と一言添えると丁寧です。
Q: のし袋は使用できますか?
A: 白無地の封筒が基本ですが、水引のない白い不祝儀袋(のし袋)を使用しても構いません。ただし、金額が高額な場合は中袋付きののし袋を選ぶとよいでしょう。
Q: 表書きの文字が小さすぎたり大きすぎたりしないか心配です
A: 封筒の大きさに対してバランスの取れた文字サイズを心がけます。一般的には、封筒の縦幅の3分の1程度の高さの文字で書くとバランスが良くなります。
まとめ
永代供養料の封筒準備では、以下のポイントを押さえることが大切です:
基本のマナー:
白無地の封筒を使用
濃い墨(筆ペン可)で縦書き
表書きは「御布施」または「永代供養料」
金額は旧漢字で記載
袱紗に包んで丁寧にお渡し
事前準備のチェックリスト:
白無地封筒の用意
筆ペンまたは墨の準備
新札(綺麗なお札)の用意
袱紗・切手盆の準備
金額の旧漢字表記の確認
寺院への渡し方・タイミングの確認
永代供養は故人を長く供養していただく大切な依頼です。正しいマナーで感謝の気持ちを込めてお納めすることで、ご家族も安心してお任せできるでしょう。不明な点があれば、遠慮なく寺院や霊園にご相談ください。
基本のマナー:
白無地の封筒を使用
濃い墨(筆ペン可)で縦書き
表書きは「御布施」または「永代供養料」
金額は旧漢字で記載
袱紗に包んで丁寧にお渡し
事前準備のチェックリスト:
白無地封筒の用意
筆ペンまたは墨の準備
新札(綺麗なお札)の用意
袱紗・切手盆の準備
金額の旧漢字表記の確認
寺院への渡し方・タイミングの確認
永代供養は故人を長く供養していただく大切な依頼です。正しいマナーで感謝の気持ちを込めてお納めすることで、ご家族も安心してお任せできるでしょう。不明な点があれば、遠慮なく寺院や霊園にご相談ください。