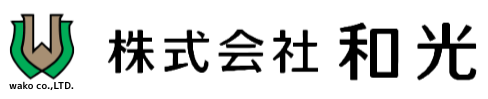通話料無料 9:00~17:30
0120‐66‐4114
浄土真宗で永代供養はできない?その理由と3つの解決策を徹底解説
投稿日:2025年8月28日

目次
- 永代供養とは?まず基礎知識をチェック
- 浄土真宗ではなぜ永代供養ができないのか
- 「亡くなれば極楽浄土へ」という即成仏の教え
- 追善供養を行わない浄土真宗
- 浄土真宗の方が永代供養するための3つの方法
- 宗派の本山に納骨する
- 永代供養塔のある浄土真宗寺院を選ぶ
- 宗旨・宗派不問の霊園(永代供養墓)を利用する
- 永代経とは?浄土真宗の法要と永代供養の違い
- 永代供養との違い
- 永代供養墓の種類と費用相場
- 合祀墓(共同墓)
- 集合墓(納骨堂など)
- 個別墓(永代供養付き個人墓)
- 浄土真宗でお墓を永代供養にする手順ガイド
- ステップ1:家族・親族との話し合い
- ステップ2:現在のお墓の管理者に相談
- ステップ3:新しい納骨先を決定
- ステップ4:改葬許可証の取得
- ステップ5:石材店に墓石撤去を依頼
- ステップ6:遷仏法要(閉眼供養)
- ステップ7:遺骨の取り出しと墓石撤去
- ステップ8:新しい供養先へ納骨
- 浄土真宗と浄土宗の違いも豆知識として紹介
- 成仏する時期の違い
- 慣習・作法の違い
- よくある質問と回答(FAQ)
- Q1. 浄土真宗のお寺に永代供養をお願いできないのですか?
- Q2. 永代供養をお願いすると浄土真宗の教えに反することになりますか?
- Q3. 永代供養墓を利用した場合、浄土真宗の法要(年忌など)はどうなりますか?
- Q4. 永代供養を申し込むと具体的にどんな供養をしてもらえるのですか?
- Q5. 永代供養の費用は一括払いとのことですが、将来追加費用は本当にかかりませんか?
- まとめ
「浄土真宗のお寺には永代供養はない」と言われて困っていませんか?後継ぎがいない場合や子供が遠方にいる場合、お墓の管理をどうすれば良いのか不安になりますよね。 本記事では、浄土真宗で永代供養ができない理由を教義の観点から分かりやすく解説し、それでも安心してお墓を任せられる3つの具体的な方法をご紹介します。費用相場や手続きの流れも詳しく説明しますので、無縁仏になる心配を解消して、安心できる供養方法を見つけてください。
永代供養とは?まず基礎知識をチェック
永代供養とは、お寺や霊園が遺骨の管理と供養を永続的に行うサービスのことです。一般的には、遺族に代わって施設側が責任を持ってお墓の維持管理や定期的な供養を行い、無縁仏になることを防ぎます。
近年、永代供養への関心が高まっている背景には、少子高齢化による後継者不足があります。「子供がいない」「子供が遠方に住んでいる」「お墓の管理負担を家族にかけたくない」といった理由で、永代供養を検討する方が増えています。
永代供養の基本的な仕組みは以下の通りです:
永代使用料:最初に一括で支払う費用
管理・供養:施設が代行して行う
法要:定期的な合同法要の実施
無縁仏防止:後継者がいなくなっても供養が続く
ただし、宗派によって永代供養に対する考え方は異なります。特に浄土真宗では、他の宗派とは異なる独特の教義があるため、永代供養について理解を深める必要があります。
近年、永代供養への関心が高まっている背景には、少子高齢化による後継者不足があります。「子供がいない」「子供が遠方に住んでいる」「お墓の管理負担を家族にかけたくない」といった理由で、永代供養を検討する方が増えています。
永代供養の基本的な仕組みは以下の通りです:
永代使用料:最初に一括で支払う費用
管理・供養:施設が代行して行う
法要:定期的な合同法要の実施
無縁仏防止:後継者がいなくなっても供養が続く
ただし、宗派によって永代供養に対する考え方は異なります。特に浄土真宗では、他の宗派とは異なる独特の教義があるため、永代供養について理解を深める必要があります。
浄土真宗ではなぜ永代供養ができないのか
浄土真宗に永代供養の概念がない理由は、この宗派独特の教義にあります。簡単に言うと、浄土真宗では「亡くなった人のために供養をする必要がない」と考えられているためです。
「亡くなれば極楽浄土へ」という即成仏の教え
浄土真宗の根本的な教えでは、阿弥陀如来の誓願によって、人は亡くなると直ちに極楽浄土に往生し成仏するとされています。つまり、死後すぐに仏様になるため、この世に魂が留まることはありません。
他の宗派では「四十九日まで霊が現世にいる」「成仏するまで時間がかかる」と考えるところもありますが、浄土真宗では「即成仏」が基本です。すでに仏様になった方に対して、さらに供養を行う必要はないという考え方なのです。
他の宗派では「四十九日まで霊が現世にいる」「成仏するまで時間がかかる」と考えるところもありますが、浄土真宗では「即成仏」が基本です。すでに仏様になった方に対して、さらに供養を行う必要はないという考え方なのです。
追善供養を行わない浄土真宗
一般的な仏教では、故人の冥福を祈り、良い行いを積むことで故人の来世での幸せを願う「追善供養」が行われます。しかし浄土真宗では、このような追善供養は行いません。
浄土真宗における法要は、故人の供養のためではなく、遺された人が仏の教えを聞く機会として位置づけられています。つまり、法要は「生きている人のため」のものであり、亡くなった方は既に成仏しているので供養は不要という考え方です。
このように、浄土真宗では根本的に「死者への供養」という概念が他宗派と異なるため、「永代供養」という発想が生まれにくいのです。
しかし、だからといって浄土真宗の人が永代にわたってお墓を任せられないのかというと、必ずしもそうではありません。実際には、浄土真宗の教えを踏まえつつ、現実的な解決策が存在します。
浄土真宗における法要は、故人の供養のためではなく、遺された人が仏の教えを聞く機会として位置づけられています。つまり、法要は「生きている人のため」のものであり、亡くなった方は既に成仏しているので供養は不要という考え方です。
このように、浄土真宗では根本的に「死者への供養」という概念が他宗派と異なるため、「永代供養」という発想が生まれにくいのです。
しかし、だからといって浄土真宗の人が永代にわたってお墓を任せられないのかというと、必ずしもそうではありません。実際には、浄土真宗の教えを踏まえつつ、現実的な解決策が存在します。
浄土真宗の方が永代供養するための3つの方法
ご安心ください。浄土真宗の方でも、実際に永代にわたってお墓を任せる方法があります。以下の3つの方法をご検討ください。
宗派の本山に納骨する
浄土真宗には「本山納骨」という制度があります。これは、浄土真宗本願寺派(西本願寺)や真宗大谷派(東本願寺)の本山にある納骨施設に遺骨を納める方法です。
本山納骨の特徴:
西本願寺の「大谷本廟」、東本願寺の「真宗本廟」に納骨
門徒のみが利用可能
費用は数万円程度から(分骨・全骨により異なる)
親鸞聖人と同じ場所で永代に供養される安心感
菩提寺を通じて申し込み
本山納骨は浄土真宗の教えに最も沿った方法であり、多くの門徒が利用しています。費用も比較的リーズナブルで、宗派の根本道場で供養を受けられるという精神的な安心感も大きなメリットです。
本山納骨の特徴:
西本願寺の「大谷本廟」、東本願寺の「真宗本廟」に納骨
門徒のみが利用可能
費用は数万円程度から(分骨・全骨により異なる)
親鸞聖人と同じ場所で永代に供養される安心感
菩提寺を通じて申し込み
本山納骨は浄土真宗の教えに最も沿った方法であり、多くの門徒が利用しています。費用も比較的リーズナブルで、宗派の根本道場で供養を受けられるという精神的な安心感も大きなメリットです。
永代供養塔のある浄土真宗寺院を選ぶ
近年、浄土真宗の寺院の中にも「永代供養塔」や合同墓を設けて、無縁仏を受け入れているところが増えています。厳密には「永代供養」ではなく「永代経法要」という形で、継続的にお経を読み続ける取り組みです。
永代供養塔利用の特徴:
浄土真宗の寺院が運営
門徒でなくても利用可能な寺院もある
永代経法要により継続的な読経
費用は寺院により異なる(30万円~100万円程度)
浄土真宗の教えに沿った供養内容
菩提寺が対応していない場合でも、他の浄土真宗寺院で受け入れてくれる場合があります。まずは近隣の浄土真宗寺院に相談してみることをおすすめします。
永代供養塔利用の特徴:
浄土真宗の寺院が運営
門徒でなくても利用可能な寺院もある
永代経法要により継続的な読経
費用は寺院により異なる(30万円~100万円程度)
浄土真宗の教えに沿った供養内容
菩提寺が対応していない場合でも、他の浄土真宗寺院で受け入れてくれる場合があります。まずは近隣の浄土真宗寺院に相談してみることをおすすめします。
宗旨・宗派不問の霊園(永代供養墓)を利用する
公営・民間を問わず、宗派不問の霊園にある永代供養墓を利用することも可能です。浄土真宗の信徒でも何の問題もなく利用できます。
宗派不問永代供養墓の特徴:
檀家になる必要がない
宗派を変える必要がない
様々なタイプから選択可能(合祀墓・納骨堂・樹木葬など)
家族に負担を残さない
全国に多数の選択肢がある
改宗する必要はないので、浄土真宗の信仰を持ち続けながら利用できます。選ぶ際は、自宅からのアクセスや霊園の経営主体の信頼性も確認しましょう。
宗派不問永代供養墓の特徴:
檀家になる必要がない
宗派を変える必要がない
様々なタイプから選択可能(合祀墓・納骨堂・樹木葬など)
家族に負担を残さない
全国に多数の選択肢がある
改宗する必要はないので、浄土真宗の信仰を持ち続けながら利用できます。選ぶ際は、自宅からのアクセスや霊園の経営主体の信頼性も確認しましょう。
永代経とは?浄土真宗の法要と永代供養の違い
浄土真宗には「永代経」という法要があります。名前が「永代供養」と似ているため混同されがちですが、全く異なるものです。
永代経とは:
正式名称は「永代読経」
寺院が代々途切れることなくお経を読み続ける法要
故人の冥福を祈るものではない
生きている人が仏縁を結ぶための法要
阿弥陀如来の教えを伝え続けることが目的
永代経とは:
正式名称は「永代読経」
寺院が代々途切れることなくお経を読み続ける法要
故人の冥福を祈るものではない
生きている人が仏縁を結ぶための法要
阿弥陀如来の教えを伝え続けることが目的
永代供養との違い
| 項目 | 永代経 | 永代供養 |
|---|---|---|
| 性質 | 法要(お経) | お墓の管理サービス |
| 目的 | 仏法を伝える | 遺骨の管理・供養 |
| 対象 | 生きている人 | 故人 |
| 費用 | 永代経懇志(数万円程度) | 永代供養料(数十万円) |
永代経法要をお願いする場合は、四十九日法要の際に住職に相談し、永代経懇志として数万円程度のお布施を包むのが一般的です。
永代供養墓の種類と費用相場
永代供養墓には主に3つのタイプがあり、それぞれ特徴と費用が異なります。
合祀墓(共同墓)
他の方の遺骨と一緒に埋葬されるタイプです。
特徴:
最も費用が安い
一度合祀すると個別の遺骨は取り出せない
合同で供養される
費用相場:5万円~30万円
特徴:
最も費用が安い
一度合祀すると個別の遺骨は取り出せない
合同で供養される
費用相場:5万円~30万円
集合墓(納骨堂など)
一定期間は個別に安置し、その後合祀するタイプです。
特徴:
個別参拝が可能(期間限定)
屋内外に個別スペースがある
期間終了後は合祀が一般的
費用相場:20万円~70万円
特徴:
個別参拝が可能(期間限定)
屋内外に個別スペースがある
期間終了後は合祀が一般的
費用相場:20万円~70万円
個別墓(永代供養付き個人墓)
個人または夫婦ごとに墓石や区画を設けるタイプです。
特徴:
通常のお墓に近い形
一定期間個別供養を受けられる
見た目の満足度が高い
費用相場:50万円~150万円
費用には永代使用料、納骨料、石材費などが含まれる場合があります。また、供養の期間や内容は施設によって異なるため、事前に詳細を確認することが重要です。
特徴:
通常のお墓に近い形
一定期間個別供養を受けられる
見た目の満足度が高い
費用相場:50万円~150万円
費用には永代使用料、納骨料、石材費などが含まれる場合があります。また、供養の期間や内容は施設によって異なるため、事前に詳細を確認することが重要です。
浄土真宗でお墓を永代供養にする手順ガイド
現在先祖代々のお墓がある場合の改葬手順をご案内します。この手順に従えば、安心して新しい供養先にご遺骨を移すことができます。
ステップ1:家族・親族との話し合い
まずは家族や親族と十分に話し合い、合意を得ましょう。お墓の移転は重要な決定なので、関係者全員の理解が必要です。
ステップ2:現在のお墓の管理者に相談
菩提寺や霊園の管理者に改葬の意向を伝え、手続きについて相談します。浄土真宗の場合は住職に永代供養の考え方についても確認しましょう。
ステップ3:新しい納骨先を決定
本山納骨、永代供養塔、宗派不問霊園の中から最適な納骨先を選択し、契約を結びます。
ステップ4:改葬許可証の取得
現在のお墓がある市町村役場で改葬許可申請を行います。必要書類は以下の通りです:
改葬許可申請書
埋葬証明書(現在の墓地管理者発行)
受入証明書(新しい納骨先発行)
改葬許可申請書
埋葬証明書(現在の墓地管理者発行)
受入証明書(新しい納骨先発行)
ステップ5:石材店に墓石撤去を依頼
墓石の撤去と整地作業を石材店に依頼します。費用は墓石の大きさにより異なりますが、30万円~100万円程度が相場です。
ステップ6:遷仏法要(閉眼供養)
浄土真宗では「遷仏法要」を行い、お墓から魂を抜く儀式を執り行います。他宗派の「閉眼供養」に相当します。
ステップ7:遺骨の取り出しと墓石撤去
遷仏法要後、遺骨を取り出し、墓石を撤去します。取り出した遺骨は清潔な骨壺に移し替えます。
ステップ8:新しい供養先へ納骨
新しい納骨先で納骨式を行います。浄土真宗の場合は住職による読経のもと、厳かに納骨します。
Point: 各ステップで必要な費用や期間は事前に確認し、スケジュールに余裕を持って進めることが大切です。
Point: 各ステップで必要な費用や期間は事前に確認し、スケジュールに余裕を持って進めることが大切です。
浄土真宗と浄土宗の違いも豆知識として紹介
ちなみに、浄土真宗と名前が似ている「浄土宗」とは、供養に対する考え方が大きく異なります。
成仏する時期の違い
浄土真宗:
死後すぐに成仏(即成仏)
阿弥陀如来の他力本願による救済
浄土宗:
死後49日間は中陰の期間
遺族の念仏や回向により成仏をサポート
死後すぐに成仏(即成仏)
阿弥陀如来の他力本願による救済
浄土宗:
死後49日間は中陰の期間
遺族の念仏や回向により成仏をサポート
慣習・作法の違い
浄土真宗:
「ご冥福をお祈りします」は使わない
位牌は用いない(法名軸を使用)
追善供養は行わない
浄土宗:
「ご冥福をお祈りします」を使用
位牌を用いる
追善供養を積極的に行う
このような違いがあるため、浄土真宗では永代供養という概念が生まれにくく、浄土宗では一般的に永代供養が受け入れられているのです。
「ご冥福をお祈りします」は使わない
位牌は用いない(法名軸を使用)
追善供養は行わない
浄土宗:
「ご冥福をお祈りします」を使用
位牌を用いる
追善供養を積極的に行う
このような違いがあるため、浄土真宗では永代供養という概念が生まれにくく、浄土宗では一般的に永代供養が受け入れられているのです。
よくある質問と回答(FAQ)
Q1. 浄土真宗のお寺に永代供養をお願いできないのですか?
A: 浄土真宗の多くの寺院では伝統的に永代供養という言葉は使いません。ただし「永代経法要を行いながら納骨壇で遺骨を預かる」など、実質的に永代供養に近い形を取っている寺もあります。まずは菩提寺に相談し、それでも難しければ本山納骨や宗派不問の永代供養墓を検討しましょう。
Q2. 永代供養をお願いすると浄土真宗の教えに反することになりますか?
A: 永代供養そのものは他宗の考え方ですが、浄土真宗の門徒であっても亡き人を思いお墓を大切にする気持ち自体は尊いものです。お墓の管理を託すこと(永代供養墓の利用)は教えに背くことではありません。むしろ残された家族が安心して念仏に向き合える環境を整える前向きな手段といえます。
Q3. 永代供養墓を利用した場合、浄土真宗の法要(年忌など)はどうなりますか?
A: 永代供養墓を利用しても、浄土真宗の年忌法要を行うことは可能です。遺骨の所在地がお寺や霊園になるだけで、ご自宅や菩提寺での法要を営むことに問題はありません。菩提寺が遠方の場合は最寄りの浄土真宗のお寺に年忌だけお願いすることもできます。
Q4. 永代供養を申し込むと具体的にどんな供養をしてもらえるのですか?
A: 一般的には春秋の彼岸やお盆などに合同法要を営んでもらえます。浄土真宗の場合、合同法要でも故人の冥福を祈る形式ではなく、阿弥陀如来の教えを聞き浄土を讃える内容になります。また、毎月の命日読経(永代経法要)をしてくれるところもあります。申し込む際には、どのタイミングでどんな読経・法要が行われるかを事前に確認しておくとよいでしょう。
Q5. 永代供養の費用は一括払いとのことですが、将来追加費用は本当にかかりませんか?
A: 基本的に永代供養料は最初に一度だけお支払いします。その後の管理費や法要料は不要という契約がほとんどです。ただし契約期間(○○回忌まで等)が定められている場合、その期間終了後に合祀する際の費用が別途かかるケースもあります。また、法要に参列する際のお布施やお車代などは都度必要です。契約内容をよく読み、不明点は事前に問い合わせておけば安心です。
まとめ
浄土真宗では確かに永代供養という概念はありませんが、現代の課題に対応した様々な解決策が用意されています。本山納骨、永代供養塔の利用、宗派不問の霊園活用など、それぞれにメリットがあります。
大切なのは、浄土真宗の教えを理解した上で、ご自身とご家族にとって最適な方法を選択することです。無縁仏になる心配をせず、安心してお墓を任せられる方法は必ず見つかります。まずは菩提寺や専門家に相談して、具体的な一歩を踏み出してみてください。
大切なのは、浄土真宗の教えを理解した上で、ご自身とご家族にとって最適な方法を選択することです。無縁仏になる心配をせず、安心してお墓を任せられる方法は必ず見つかります。まずは菩提寺や専門家に相談して、具体的な一歩を踏み出してみてください。