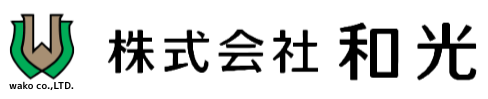通話料無料 9:00~17:30
0120‐66‐4114
樹木葬と散骨の違い徹底ガイド|後悔しない選び方と費用・手続きまで解説
投稿日:2025年8月21日

目次
- 樹木葬とは何?自然に還る新しいお墓のかたち
- 樹木葬の主な種類
- 散骨とは何?故人を自然に還す葬送スタイル
- 散骨の主な種類
- 樹木葬と散骨が選ばれる理由 – 増える背景を読み解く
- 選ばれる主な理由
- 樹木葬と散骨の違いを比較 – 方法・費用・供養形式の徹底比較
- 遺骨の扱い方の違い
- 法律・手続きの違い
- 墓標・供養形態の違い
- 費用の違い
- 維持管理とアフターケアの違い
- 主な違いまとめ
- 樹木葬のメリット
- 樹木葬のデメリット
- 散骨のメリット
- 散骨のデメリット
- どちらを選ぶ?後悔しないための選択ポイント
- よくある質問と回答(FAQ)
- Q1: 散骨は法律的に問題ないのでしょうか?
- Q2: 樹木葬を利用するにはどんな手続きが必要ですか?
- Q3: 散骨する際、遺骨は粉にしないといけませんか?
- Q4: 樹木葬と散骨ではどちらが費用を安く抑えられますか?
- Q5: 散骨した後に故人を弔うにはどうすればいいですか?
- Q6: 樹木葬はどこの霊園でもできますか?
- まとめ – 自然に還る供養を選ぶあなたへ
樹木葬と散骨、どちらを選べばよいかお悩みではありませんか?自然に還る新しい供養方法として注目を集めているこの2つの選択肢について、それぞれの特徴や費用の違いはもちろん、選び方のポイントまで丁寧に解説します。本記事を読めば、ご自身やご家族にとって最適な供養方法の判断材料が得られ、後悔のない選択ができるようになります。
樹木葬とは何?自然に還る新しいお墓のかたち
樹木葬(じゅもくそう)は、墓石の代わりに樹木や花をシンボルとし、その下に遺骨を埋葬する供養方法です。従来のお墓のように石碑を建てるのではなく、シンボルツリーが故人の印となります。
日本初の樹木葬は1999年に岩手県の祥雲寺で始まり、近年では都市部を含め全国に広がっています。樹木葬には以下のような種類があります:
日本初の樹木葬は1999年に岩手県の祥雲寺で始まり、近年では都市部を含め全国に広がっています。樹木葬には以下のような種類があります:
樹木葬の主な種類
・里山型:自然の山林に埋葬する最も自然に近いスタイル
・公園型:整備された公園風の区画で、アクセスが良い都市近郊型
・都市型:都市部の霊園内に設けられた樹木葬専用区画
また、埋葬方法によって「個別型(専用区画)」と「合祀型(他の方と一緒)」に分かれます。多くの樹木葬は永代供養となっており、霊園や寺院が遺骨を管理・供養してくれるため、後継者がいない方でも安心して利用できます。
樹木葬墓地は墓石がなく明るい雰囲気で、まるで自然公園のような開放的な空間が特徴です。桜やハナミズキなどの季節の花を楽しめる霊園も多く、従来のお墓に抵抗がある方にも受け入れられやすい環境となっています。
・公園型:整備された公園風の区画で、アクセスが良い都市近郊型
・都市型:都市部の霊園内に設けられた樹木葬専用区画
また、埋葬方法によって「個別型(専用区画)」と「合祀型(他の方と一緒)」に分かれます。多くの樹木葬は永代供養となっており、霊園や寺院が遺骨を管理・供養してくれるため、後継者がいない方でも安心して利用できます。
樹木葬墓地は墓石がなく明るい雰囲気で、まるで自然公園のような開放的な空間が特徴です。桜やハナミズキなどの季節の花を楽しめる霊園も多く、従来のお墓に抵抗がある方にも受け入れられやすい環境となっています。
散骨とは何?故人を自然に還す葬送スタイル
散骨(さんこつ)とは、火葬した遺骨を細かく砕き、海や山など自然の中に撒く葬送方法です。日本では1990年代から注目され始め、自然に還りたいと願う方々に選ばれています。
散骨の主な種類
・海洋散骨:船で沖合に出て海に撒く、最もポピュラーな方法
・山林散骨:山や森に撒く方法(土地所有者の許可が必要)
・空中散骨:セスナ機や気球などで上空から撒く空中葬
法律上、散骨は明確に禁止されていません。警察庁は1991年に「葬送のため節度をもって行う分には問題なし」との見解を示しており、適切に行われる散骨は違法ではないとされています。ただし、自治体によっては禁止区域を設けている場合もあり、周囲への配慮が重要です。
散骨を行う際は、遺骨を必ず細かく粉骨する(直径2mm以下推奨)、私有地や人が集まる場所は避ける、船舶での散骨では海上保安庁への届け出が必要な場合があるなど、いくつかのルールがあります。多くの場合、専門業者に依頼することで適切に実施できます。
・山林散骨:山や森に撒く方法(土地所有者の許可が必要)
・空中散骨:セスナ機や気球などで上空から撒く空中葬
法律上、散骨は明確に禁止されていません。警察庁は1991年に「葬送のため節度をもって行う分には問題なし」との見解を示しており、適切に行われる散骨は違法ではないとされています。ただし、自治体によっては禁止区域を設けている場合もあり、周囲への配慮が重要です。
散骨を行う際は、遺骨を必ず細かく粉骨する(直径2mm以下推奨)、私有地や人が集まる場所は避ける、船舶での散骨では海上保安庁への届け出が必要な場合があるなど、いくつかのルールがあります。多くの場合、専門業者に依頼することで適切に実施できます。
樹木葬と散骨が選ばれる理由 – 増える背景を読み解く
従来は亡くなればお墓に納骨するのが一般的でしたが、近年ではお墓を持たない選択をする人が増えています。この背景には以下のような社会的要因があります。
選ばれる主な理由
・後継者不足:少子高齢化でお墓を継ぐ人がいないケースが増加し、無縁仏を避けるため継承者不要な永代供養墓や樹木葬を選ぶ
・費用負担の軽減:お墓の建立費用や管理費が高く、散骨や樹木葬なら費用を抑えられる
・ライフスタイルの変化:都市部への移住で実家のお墓参りが困難になり、お墓に縛られない供養を求める
・自然志向の高まり:「自然に還りたい」「緑に囲まれて眠りたい」という価値観の広がり
実際のデータを見ると、変化の大きさがわかります。墓地紹介大手の鎌倉新書による調査では、2024年に新たに購入されたお墓の48.7%が樹木葬だったことが報告されています。14年前には樹木葬は1割未満だったことを考えると、急速な変化と言えるでしょう。
個人の価値観の多様化も大きな要因です。宗教観の変化や終活ブームで、自分らしい葬送を選ぶ人が増えており、樹木葬・散骨はそうした新しいニーズに応える選択肢として注目されています。
・費用負担の軽減:お墓の建立費用や管理費が高く、散骨や樹木葬なら費用を抑えられる
・ライフスタイルの変化:都市部への移住で実家のお墓参りが困難になり、お墓に縛られない供養を求める
・自然志向の高まり:「自然に還りたい」「緑に囲まれて眠りたい」という価値観の広がり
実際のデータを見ると、変化の大きさがわかります。墓地紹介大手の鎌倉新書による調査では、2024年に新たに購入されたお墓の48.7%が樹木葬だったことが報告されています。14年前には樹木葬は1割未満だったことを考えると、急速な変化と言えるでしょう。
個人の価値観の多様化も大きな要因です。宗教観の変化や終活ブームで、自分らしい葬送を選ぶ人が増えており、樹木葬・散骨はそうした新しいニーズに応える選択肢として注目されています。
樹木葬と散骨の違いを比較 – 方法・費用・供養形式の徹底比較
樹木葬と散骨の主な違いを、複数の観点から詳しく比較していきます。
遺骨の扱い方の違い
樹木葬は遺骨を土中に埋葬します。一方、散骨は遺骨を細かく砕いて撒きます。
樹木葬では骨壺のまま埋める場合と、布袋等に移して埋める場合があります。埋葬後も遺骨は土中に残り続けます。散骨では遺骨をパウダー状(直径2mm以下推奨)に粉骨して撒くのが一般的で、遺骨は自然に返り手元には残りません。
樹木葬では骨壺のまま埋める場合と、布袋等に移して埋める場合があります。埋葬後も遺骨は土中に残り続けます。散骨では遺骨をパウダー状(直径2mm以下推奨)に粉骨して撒くのが一般的で、遺骨は自然に返り手元には残りません。
法律・手続きの違い
樹木葬は法律上「埋葬」に当たるため、墓地埋葬法の規定に従います。墓地として許可された土地でしか行えず、埋葬時には役所発行の埋葬許可証が必要です。
一方、散骨には明確な法律がなく、節度をもって行われる限り届け出や許可は不要です。ただし散骨も全くノールールではありません。自治体によっては禁止区域を設けている場合や、周辺住民への配慮が求められます。
一方、散骨には明確な法律がなく、節度をもって行われる限り届け出や許可は不要です。ただし散骨も全くノールールではありません。自治体によっては禁止区域を設けている場合や、周辺住民への配慮が求められます。
墓標・供養形態の違い
樹木葬ではシンボルとなる樹木やプレートが設置されるため、遺骨の場所を特定できます。**個別区画ならその木の下に故人が眠っているとわかるので、お墓参りの際は直接その場所で手を合わせられます。
一方、散骨は遺骨を自然に返してしまうため、特定の参拝場所が残りません。**海に撒いた場合は海原全体が供養の場とも言えますが、後日「ここに遺骨がある」という場所は存在しないことになります。
ただし、散骨でも年に一度散骨ポイント付近に行き献花するご遺族もいます。また、一部業者は散骨位置の緯度経度を記録し証明書を発行してくれるので、それを心の拠り所にするケースもあります。
一方、散骨は遺骨を自然に返してしまうため、特定の参拝場所が残りません。**海に撒いた場合は海原全体が供養の場とも言えますが、後日「ここに遺骨がある」という場所は存在しないことになります。
ただし、散骨でも年に一度散骨ポイント付近に行き献花するご遺族もいます。また、一部業者は散骨位置の緯度経度を記録し証明書を発行してくれるので、それを心の拠り所にするケースもあります。
費用の違い
費用面では散骨の方が総じて安価です。樹木葬は永代使用料や埋葬料を含め平均10~50万円ほどかかりますが、散骨はプランにもよりますが5~20万円程度が相場です。
具体的な費用例
・樹木葬:個別区画30万円~、合祀プラン10万円~
・散骨:家族貸切プラン20万円前後、業者任せの合同散骨5~6万円程度
ただしケースによって異なります。樹木葬でもオプションでプレートを立てれば追加費用が発生しますし、散骨でも粉骨代や船上供養式の費用がかかれば高くなります。一般的には散骨の方が費用負担は軽めと言えるでしょう。
具体的な費用例
・樹木葬:個別区画30万円~、合祀プラン10万円~
・散骨:家族貸切プラン20万円前後、業者任せの合同散骨5~6万円程度
ただしケースによって異なります。樹木葬でもオプションでプレートを立てれば追加費用が発生しますし、散骨でも粉骨代や船上供養式の費用がかかれば高くなります。一般的には散骨の方が費用負担は軽めと言えるでしょう。
維持管理とアフターケアの違い
樹木葬は多くの場合永代供養が付いており、霊園や寺院が将来にわたって遺骨を管理・供養してくれます。そのため後継者がいなくても無縁仏になる心配は少なく、管理料も基本不要です(霊園によっては多少の管理費がある場合も)。
散骨は遺骨そのものの管理は不要ですが、一度撒いたら取り戻せないため将来別の墓に移すことは不可能です。また散骨後に故人を偲ぶ場は自分で工夫して作る必要があります(例えば手元供養や記念樹を植える等)。
散骨は遺骨そのものの管理は不要ですが、一度撒いたら取り戻せないため将来別の墓に移すことは不可能です。また散骨後に故人を偲ぶ場は自分で工夫して作る必要があります(例えば手元供養や記念樹を植える等)。
主な違いまとめ
| 項目 | 樹木葬 | 散骨 |
|---|---|---|
| 遺骨の扱い | 土に埋める | 自然に撒く |
| 法的手続き | 埋葬許可証が必要 | 特別な許可不要 |
| 費用相場 | 10〜50万円 | 5〜20万円 |
| お参り | 可能(墓地で) | 困難(場所特定できず) |
| 管理 | 霊園が永代管理 | 管理不要(自然に返る) |
樹木葬のメリット
お墓の承継者が不要 – 永代供養で寺院等が管理してくれる場合が多く、子孫に負担を残さない
費用が比較的安い – 一般的なお墓建立に比べれば費用が低く、墓石代も不要のため経済的
自然に還れる安心感 – 「緑に囲まれて眠れる」「故人が自然の一部になる」という精神的な満足が得られる
明るい雰囲気 – 墓石墓所よりも公園のような開放的空間で、従来のお墓に抵抗がある人にも受け入れられやすい
宗派不問が多い – 寺院管理でも無宗教OKが多く、誰でも利用しやすい
費用が比較的安い – 一般的なお墓建立に比べれば費用が低く、墓石代も不要のため経済的
自然に還れる安心感 – 「緑に囲まれて眠れる」「故人が自然の一部になる」という精神的な満足が得られる
明るい雰囲気 – 墓石墓所よりも公園のような開放的空間で、従来のお墓に抵抗がある人にも受け入れられやすい
宗派不問が多い – 寺院管理でも無宗教OKが多く、誰でも利用しやすい
樹木葬のデメリット
希望の霊園が確保できない可能性 – 実施霊園が限られ人気も高いため、場所によっては空き待ちになることも
アクセスが悪い場合がある – 自然豊かな立地ゆえ郊外や山間部が多く、お参りに行きにくいケースもある
シンボルツリーの維持 – 樹木や花は生き物なので、枯れたり台風で倒れたりするリスクがある
合祀型では場所が特定できない – 合同で埋葬する場合、遺骨が混ざり合い具体的な「自分の遺骨の場所」はわからなくなる
従来のお墓と違うため親族の理解が必要 – 特に年配の方には「墓に入らないのは可哀想」と感じる人もいる
アクセスが悪い場合がある – 自然豊かな立地ゆえ郊外や山間部が多く、お参りに行きにくいケースもある
シンボルツリーの維持 – 樹木や花は生き物なので、枯れたり台風で倒れたりするリスクがある
合祀型では場所が特定できない – 合同で埋葬する場合、遺骨が混ざり合い具体的な「自分の遺骨の場所」はわからなくなる
従来のお墓と違うため親族の理解が必要 – 特に年配の方には「墓に入らないのは可哀想」と感じる人もいる
散骨のメリット
費用負担が軽い – 墓地代や墓石代が不要で、葬送方法の中でも安価に済ませられる
維持管理の手間なし – 供養後に墓守や清掃などの必要がなく、遠方に住んでいても問題ない
故人の希望を叶えやすい – 海が好きだったから海へ、山が好きだったから山へ等、思い入れの場所に還してあげられる
形式にとらわれない自由さ – 宗教・宗派も問わず、自宅でお別れ会だけ行って散骨するなど、自由な発想で見送りができる
自然志向の人に合う – 完全に自然へ帰すことで「地球に還元できた」という満足を感じる人もいる
維持管理の手間なし – 供養後に墓守や清掃などの必要がなく、遠方に住んでいても問題ない
故人の希望を叶えやすい – 海が好きだったから海へ、山が好きだったから山へ等、思い入れの場所に還してあげられる
形式にとらわれない自由さ – 宗教・宗派も問わず、自宅でお別れ会だけ行って散骨するなど、自由な発想で見送りができる
自然志向の人に合う – 完全に自然へ帰すことで「地球に還元できた」という満足を感じる人もいる
散骨のデメリット
遺骨が手元に残らない – 全て撒いてしまうので後から「やはり手元に少し置いておけば…」と寂しさを感じる可能性がある
お墓参りの場が無い – 故人に会いに行く"場所"が無いため、供養の実感が薄れると感じる人もいる
親族の理解が必要 – 世代によっては散骨に抵抗感が強く、反対されるケースもある
場所・方法に制約 – どこでも撒ける訳ではなく、陸地は私有地以外NG、海も岸辺は避け沖合へ行く必要などルールがある
取り返しがつかない – 一度撒いたら回収できないため、後悔してもやり直しがきかない
※メリット・デメリットは感じ方によります。故人と遺族にとって何を重視するかで選択が変わるでしょう。
お墓参りの場が無い – 故人に会いに行く"場所"が無いため、供養の実感が薄れると感じる人もいる
親族の理解が必要 – 世代によっては散骨に抵抗感が強く、反対されるケースもある
場所・方法に制約 – どこでも撒ける訳ではなく、陸地は私有地以外NG、海も岸辺は避け沖合へ行く必要などルールがある
取り返しがつかない – 一度撒いたら回収できないため、後悔してもやり直しがきかない
※メリット・デメリットは感じ方によります。故人と遺族にとって何を重視するかで選択が変わるでしょう。
どちらを選ぶ?後悔しないための選択ポイント
樹木葬か散骨か迷っている方に向けて、具体的な判断基準をご提案します。
選択のポイント
「お墓参りの場を残したい」なら → 樹木葬がおすすめ(シンボルツリーのもと手を合わせられるため)
「できるだけ費用を抑えたい」なら → 散骨が向いている(墓地代不要で安価に済ませられるため)
「遺骨はすべて自然に返したい」なら → 散骨が叶えてくれる(遺骨を残さずすべて撒けるため)
「子や親族に将来の負担をかけたくない」なら → どちらも適している(樹木葬も散骨も後継者不要。ただし樹木葬は霊園任せにでき、散骨はそもそも供養管理なし)
「親族の理解が得られるか不安」なら → 樹木葬が無難(散骨より抵抗が少なく相談しやすい)
「故人の意志を最優先したい」なら → 故人の希望に沿う方を(その希望が散骨であれば散骨、特に無ければ双方検討)
決め手になるのは何を優先したいかです。費用なのか、供養の実感なのか、自然への想いなのか、ご家族の意向なのか、ご自身の価値観を整理してみましょう。
もし迷いが晴れない場合は、実際に霊園や業者に問い合わせてみるのがおすすめです。話を聞く中で気持ちが固まることもあります。
選択のポイント
「お墓参りの場を残したい」なら → 樹木葬がおすすめ(シンボルツリーのもと手を合わせられるため)
「できるだけ費用を抑えたい」なら → 散骨が向いている(墓地代不要で安価に済ませられるため)
「遺骨はすべて自然に返したい」なら → 散骨が叶えてくれる(遺骨を残さずすべて撒けるため)
「子や親族に将来の負担をかけたくない」なら → どちらも適している(樹木葬も散骨も後継者不要。ただし樹木葬は霊園任せにでき、散骨はそもそも供養管理なし)
「親族の理解が得られるか不安」なら → 樹木葬が無難(散骨より抵抗が少なく相談しやすい)
「故人の意志を最優先したい」なら → 故人の希望に沿う方を(その希望が散骨であれば散骨、特に無ければ双方検討)
決め手になるのは何を優先したいかです。費用なのか、供養の実感なのか、自然への想いなのか、ご家族の意向なのか、ご自身の価値観を整理してみましょう。
もし迷いが晴れない場合は、実際に霊園や業者に問い合わせてみるのがおすすめです。話を聞く中で気持ちが固まることもあります。
よくある質問と回答(FAQ)
Q1: 散骨は法律的に問題ないのでしょうか?
A: 日本には散骨を明確に禁止する法律はなく、節度をもって行われる散骨は違法ではないとされています。ただし周囲への配慮や自治体の条例遵守が必要です。心配な場合は専門業者に相談すると安心です。
Q2: 樹木葬を利用するにはどんな手続きが必要ですか?
A: 樹木葬は墓地での埋葬になるため、通常のお墓と同様に埋葬許可証が必要です(火葬後に役所で発行)。霊園や寺院と契約を交わし永代使用料を支払えば、あとの管理や供養は任せられます。
Q3: 散骨する際、遺骨は粉にしないといけませんか?
A: はい、遺骨をそのままの形で撒くことは避けるべきです。散骨時には遺骨をパウダー状に粉骨するのが一般的なマナーであり、識別不能な状態にすることで周囲の理解も得やすくなります。粉骨は専門業者に依頼することも可能です。
Q4: 樹木葬と散骨ではどちらが費用を安く抑えられますか?
A: 一般的には散骨の方が費用を安くできる傾向です。樹木葬は永代供養料込みで平均10~50万円ほどかかるのに対し、散骨はプランにもよりますが5~20万円程度が目安です。ただし希望内容に合わせて見積もりを取ることをおすすめします。
Q5: 散骨した後に故人を弔うにはどうすればいいですか?
A: 散骨後は物理的なお墓が残りませんが、年忌法要の際に散骨海域の近くで献花クルーズに参加したり、自宅に故人の写真や遺影を飾って手を合わせるなどの方法があります。海洋散骨業者が合同供養祭を開催している場合もあります。
Q6: 樹木葬はどこの霊園でもできますか?
A: 樹木葬を実施している霊園・墓地は限られています。専用区画を持つ寺院や公営霊園が中心で、都会より郊外に多い傾向です。また人気が高まっており予約待ちの所もあります。気になる霊園は早めに問い合わせ、見学してみると良いでしょう。
まとめ – 自然に還る供養を選ぶあなたへ
樹木葬と散骨はどちらも伝統のお墓にとらわれない新しい供養です。それぞれに良さと注意点があり、どちらが正解というものではありません。
費用や手間を抑えたいなら散骨、故人を身近に感じたいなら樹木葬、といった風に重視するポイントに沿って選択することが大切です。
**大切なのは故人と遺族が納得できる形を選ぶことです。**本記事がお役に立ち、あなたにとって悔いのない選択ができますよう願っています。
費用や手間を抑えたいなら散骨、故人を身近に感じたいなら樹木葬、といった風に重視するポイントに沿って選択することが大切です。
**大切なのは故人と遺族が納得できる形を選ぶことです。**本記事がお役に立ち、あなたにとって悔いのない選択ができますよう願っています。