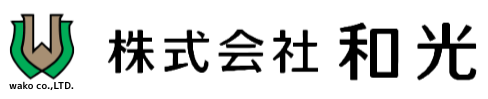通話料無料 9:00~17:30
0120‐66‐4114
浄土真宗で永代供養はできないって本当?教えの理由と3つの解決策
投稿日:2025年9月11日

目次
- 永代供養とは?浄土真宗の教えから見る供養観
- 永代供養の基本的な考え方
- 浄土真宗の独特な供養観
- 浄土真宗で永代供養ができないと言われる理由と「永代経」
- なぜ「永代供養」がないのか?
- 「永代経」との違いを理解しよう
- 浄土真宗の方が永代供養墓を利用するための3つの方法
- 方法① 菩提寺に相談し永代供養の希望を伝える
- 方法② 浄土真宗の永代供養墓がある寺院を探す
- 方法③ 宗派不問の霊園・永代供養墓を利用する
- 方法④ 宗派の本山(西本願寺・東本願寺)に納骨する
- 永代供養墓の種類別メリット・デメリットと費用相場
- 合祀墓(ごうしぼ)
- 集合墓(しゅうごうぼ)
- 個人墓・永代供養付墓(単独墓)
- 浄土真宗でのお布施・法要Q&A(マナーと豆知識)
- 年忌法要について
- 浄土真宗特有のマナー
- よくある質問(FAQ) - 浄土真宗の永代供養に関する疑問
- Q1: 浄土真宗だと本当に永代供養はできないのですか?
- Q2: 浄土真宗のお寺に「永代供養したい」と相談しても大丈夫?
- Q3: 永代供養墓を利用すると浄土真宗を離れることになりますか?
- Q4: 永代供養墓の費用は一括払いだけ?後から追加費用は?
- Q5: 浄土真宗の本山納骨をするにはどうすればいいですか?
- Q6: 浄土真宗では葬儀や法事のとき「御冥福をお祈りします」はNGって本当?
- まとめ - 浄土真宗でも自分に合った供養の形がきっと見つかる
「浄土真宗では永代供養ができない」と聞いて不安になっていませんか?後継ぎがいない、遠方に住んでいるなどの理由でお墓の将来を心配されている方も多いでしょう。 実は、浄土真宗の方でも永代にわたる供養を安心して任せられる方法があります。この記事では、浄土真宗の教えと永代供養の関係、そして具体的な解決策について詳しく解説いたします。
永代供養とは?浄土真宗の教えから見る供養観
永代供養の基本的な考え方
永代供養とは、家族に代わって寺院や霊園が永続的に故人の供養と墓地の管理を行う仕組みです。少子高齢化により墓の継承者がいない家庭が増える中、注目を集めている供養形態です。
一般的な仏教では、故人の冥福を祈り、善を積むことで故人の成仏を助けるという「追善供養」の考え方があります。これが永代供養の根底にある思想です。
一般的な仏教では、故人の冥福を祈り、善を積むことで故人の成仏を助けるという「追善供養」の考え方があります。これが永代供養の根底にある思想です。
浄土真宗の独特な供養観
一方、浄土真宗では他の仏教宗派とは異なる供養観を持っています。浄土真宗の教えでは:
他力本願:阿弥陀如来の力により救済される
即成仏:亡くなると直ちに極楽浄土で成仏する
追善供養不要:故人のために善を積む必要がない
このため、浄土真宗では「故人の冥福を祈る」という概念そのものが存在しません。亡くなった方はすでに阿弥陀仏によって救われ、極楽浄土で安らかに過ごしているからです。
他力本願:阿弥陀如来の力により救済される
即成仏:亡くなると直ちに極楽浄土で成仏する
追善供養不要:故人のために善を積む必要がない
このため、浄土真宗では「故人の冥福を祈る」という概念そのものが存在しません。亡くなった方はすでに阿弥陀仏によって救われ、極楽浄土で安らかに過ごしているからです。
浄土真宗で永代供養ができないと言われる理由と「永代経」
なぜ「永代供養」がないのか?
浄土真宗で永代供養が行われない理由は、教義にあります:
供養の必要性がない:故人はすでに成仏しているため、追善供養は不要
教えとの矛盾:「供養で故人を助ける」という発想が他力本願の教えに合わない
実践面の違い:墓じまい時も閉眼供養ではなく「遷座法要」で対応
供養の必要性がない:故人はすでに成仏しているため、追善供養は不要
教えとの矛盾:「供養で故人を助ける」という発想が他力本願の教えに合わない
実践面の違い:墓じまい時も閉眼供養ではなく「遷座法要」で対応
「永代経」との違いを理解しよう
浄土真宗には「永代経(えいたいきょう)」という似た言葉がありますが、永代供養とは全く異なります:
永代経とは
阿弥陀仏の教えを後世に伝えるための法要
故人のためではなく、仏法継承が目的
年に1〜2回程度、定期的に開催
参加費用は「永代経懇志」として寄付
故人のためではなく、仏法継承が目的
年に1〜2回程度、定期的に開催
参加費用は「永代経懇志」として寄付
永代供養との違い
永代経:仏法を未来に伝える行事
永代供養:故人の冥福を祈る供養行為
永代供養:故人の冥福を祈る供養行為
浄土真宗の方が永代供養墓を利用するための3つの方法
教義上は永代供養と言わなくても、実際には浄土真宗の方でも永代にわたる供養が可能です。以下の3つの方法をご紹介します。
方法① 菩提寺に相談し永代供養の希望を伝える
まず現在お付き合いのある浄土真宗の菩提寺がある場合、住職に「跡継ぎがいないので永代供養墓を利用したい」と相談しましょう。
メリット
慣れ親しんだお寺で安心
宗派に沿った供養が期待できる
費用が比較的抑えられる場合が多い
最近は浄土真宗のお寺でも、門徒向けに永代供養的な設備(合祀墓や納骨堂)を設けている場合があります。「永代供養」という名称は使わなくても、同様のサービスを提供していることがあるのです。
もし菩提寺で対応が難しい場合でも、他の方法がありますので心配しすぎる必要はありません。
宗派に沿った供養が期待できる
費用が比較的抑えられる場合が多い
最近は浄土真宗のお寺でも、門徒向けに永代供養的な設備(合祀墓や納骨堂)を設けている場合があります。「永代供養」という名称は使わなくても、同様のサービスを提供していることがあるのです。
もし菩提寺で対応が難しい場合でも、他の方法がありますので心配しすぎる必要はありません。
方法② 浄土真宗の永代供養墓がある寺院を探す
菩提寺で対応不可の場合、自宅近くや希望エリアで浄土真宗が運営する永代供養墓付き寺院を探しましょう。
具体的な探し方
インターネットで「(地域名) 浄土真宗 永代供養墓」を検索
霊園紹介サイトで条件を指定して検索
何件か資料請求・問い合わせをして比較検討
霊園紹介サイトで条件を指定して検索
何件か資料請求・問い合わせをして比較検討
問い合わせ時の確認ポイント
利用料金と内訳
埋葬方法(合祀・個別安置期間など)
年間管理費の有無
法要の実施内容
数は多くありませんが、浄土真宗で永代供養墓を運営する寺院は存在します。
埋葬方法(合祀・個別安置期間など)
年間管理費の有無
法要の実施内容
数は多くありませんが、浄土真宗で永代供養墓を運営する寺院は存在します。
方法③ 宗派不問の霊園・永代供養墓を利用する
浄土真宗にこだわらない場合、宗旨宗派不問の公営・民営霊園の永代供養プランを利用する方法があります。
メリット
全国各地に選択肢が豊富
檀家になる必要がない
費用を抑えられることが多い
宗派の制約を受けない
檀家になる必要がない
費用を抑えられることが多い
宗派の制約を受けない
留意点
浄土真宗の法要は基本的に行われない
菩提寺との今後の付き合い方を検討する必要
信仰のこだわりが少ない方には、現実的で費用も抑えられる選択肢です。
菩提寺との今後の付き合い方を検討する必要
信仰のこだわりが少ない方には、現実的で費用も抑えられる選択肢です。
方法④ 宗派の本山(西本願寺・東本願寺)に納骨する
浄土真宗ならではの選択肢として、本山への納骨があります。
西本願寺(本願寺派)
京都の大谷本廟で受け入れ
親鸞聖人の墓所近くに納骨可能
親鸞聖人の墓所近くに納骨可能
東本願寺(大谷派)
京都の大谷祖廟で受け入れ
本山の永代経法要でご供養
本山の永代経法要でご供養
利用方法
菩提寺に本山納骨の希望を相談
紹介状や必要書類を準備
永代経懇志を納める(金額は志次第)
親鸞聖人ゆかりの地に眠れる安心感があり、宗派の枠組みで供養を受けたい方に適しています。
紹介状や必要書類を準備
永代経懇志を納める(金額は志次第)
親鸞聖人ゆかりの地に眠れる安心感があり、宗派の枠組みで供養を受けたい方に適しています。
永代供養墓の種類別メリット・デメリットと費用相場
永代供養墓には主に3つのタイプがあります。それぞれの特徴と費用相場をご紹介します。
合祀墓(ごうしぼ)
特徴
複数の遺骨を他人と一緒に埋葬
個別のスペースはなし
共同の墓石やモニュメントで供養
費用相場:5~30万円程度
個別のスペースはなし
共同の墓石やモニュメントで供養
費用相場:5~30万円程度
メリット
最も費用が安い
年間管理費が不要な場合が多い
宗教不問が一般的
年間管理費が不要な場合が多い
宗教不問が一般的
デメリット
一度合祀すると遺骨の取り出しができない
個別のお参りスペースがない
個別のお参りスペースがない
集合墓(しゅうごうぼ)
特徴
シンボルとなる墓石の下に個別区画
一定期間個別安置後、合祀されることが多い
合祀墓と個人墓の中間的な形態
費用相場:20~70万円程度
一定期間個別安置後、合祀されることが多い
合祀墓と個人墓の中間的な形態
費用相場:20~70万円程度
メリット
個人墓より安価
一定期間は遺骨の取り出しが可能
ある程度の個別感がある
一定期間は遺骨の取り出しが可能
ある程度の個別感がある
デメリット
最終的には合祀される契約が多い
管理費が必要な場合がある
管理費が必要な場合がある
個人墓・永代供養付墓(単独墓)
特徴
従来型の墓石を建てる
継承者は不要
一定期間後に合祀に移行する契約が一般的
費用相場:50~150万円程度
継承者は不要
一定期間後に合祀に移行する契約が一般的
費用相場:50~150万円程度
メリット
費用が最も高額
年間管理費が必要な場合が多い
契約期間終了後は合祀される
年間管理費が必要な場合が多い
契約期間終了後は合祀される
デメリット
費用が最も高額
年間管理費が必要な場合が多い
契約期間終了後は合祀される
費用選択のポイント
費用感は地域や設備によって大きく異なります。契約前に以下を確認しましょう:
一時金以外の年間費用の有無
個別安置期間の長さ
期間終了後の取り扱い
年間管理費が必要な場合が多い
契約期間終了後は合祀される
費用選択のポイント
費用感は地域や設備によって大きく異なります。契約前に以下を確認しましょう:
一時金以外の年間費用の有無
個別安置期間の長さ
期間終了後の取り扱い
浄土真宗でのお布施・法要Q&A(マナーと豆知識)
浄土真宗のお布施や法要には、他宗派と異なる特徴があります。
年忌法要について
浄土真宗でも一般的な年忌法要は行われます:
1周忌、3回忌、7回忌、13回忌、17回忌、25回忌、33回忌、50回忌
1周忌、3回忌、7回忌、13回忌、17回忌、25回忌、33回忌、50回忌
浄土真宗特有のマナー
戒名ではなく「法名」
浄土真宗では戒名料は不要
法名のみで戒名は付けない
法名のみで戒名は付けない
お布施の特徴
他宗派より金額は控えめな傾向
封筒には薄墨は使わず、黒字で記入
水引は紅白の結び切りを使用
封筒には薄墨は使わず、黒字で記入
水引は紅白の結び切りを使用
言葉遣いの注意
「ご冥福をお祈りします」は使わない
「ご愁傷様です」や「ご遷化の報に接し…」を使用
「ご愁傷様です」や「ご遷化の報に接し…」を使用
永代経懇志の包み方
表書きは「永代経懇志」
金額は1万円~数十万円と幅がある
寺院によって異なるため事前確認が必要
金額は1万円~数十万円と幅がある
寺院によって異なるため事前確認が必要
よくある質問(FAQ) - 浄土真宗の永代供養に関する疑問
Q1: 浄土真宗だと本当に永代供養はできないのですか?
A1: 教義上は「永代供養」という考え方はありませんが、現実には永代供養墓を利用することは可能です。浄土真宗の教えでは亡くなった後の供養は不要とされますが、墓の継承者がいない場合などは、宗派に関係なく利用できる永代供養墓や浄土真宗の寺院が用意した合祀墓などを活用できます。要は呼び方や考え方の違いであって、浄土真宗の方でも安心して永代に渡る供養を任せるお墓は選べるのです。
Q2: 浄土真宗のお寺に「永代供養したい」と相談しても大丈夫?
A2: はい、まずは菩提寺に率直に相談することをおすすめします。浄土真宗のお寺によっては「永代供養」という言葉自体は使わなくても、同様の仕組み(永代供養墓や永代経による合同供養塔など)を用意している場合があります。相談する際は「後継ぎがいないのでお墓の管理をお願いできる方法が知りたい」という趣旨で尋ねると良いでしょう。それでも難しい場合、住職から他の受け入れ先を紹介してもらえることもありますし、本記事で紹介した他の方法を検討すれば大丈夫です。
Q3: 永代供養墓を利用すると浄土真宗を離れることになりますか?
A3: いいえ、宗派不問の霊園を利用しても信仰を捨てる必要はありません。永代供養墓はお墓の管理形態の問題であり、浄土真宗の門徒であることと両立可能です。もし菩提寺を離れる(離檀する)場合でも、多くの霊園は特定の宗派に改宗を求めません。浄土真宗の教えを心に持ちながら、実際のお墓は宗教自由の施設にする方も増えています。重要なのはご自身・ご家族が納得し安心できる供養先を選ぶことで、形式よりも心の持ちようです。
Q4: 永代供養墓の費用は一括払いだけ?後から追加費用は?
A4: 多くの場合、永代供養墓の利用料は最初の契約時に一括払いする形です。その中に「永代に亘る供養・管理費」が含まれているため、年間管理費が不要なプランもあります。ただし施設によっては一定期間ごとに管理費が必要だったり、個別安置期間終了後に合祀へ移る際に追加費用が発生するケースもあります。契約前に「永代使用料以外にかかる費用」「何年後に合祀か」などを確認しましょう。また、浄土真宗のお寺で永代経をお願いする場合は別途お布施(永代経懇志)を包む必要がありますが、金額は寺院ごと・お気持ち次第です。
Q5: 浄土真宗の本山納骨をするにはどうすればいいですか?
A5: 浄土真宗本願寺派(西本願寺)なら京都の大谷本廟、真宗大谷派(東本願寺)なら大谷祖廟が門徒向けの納骨施設を設けています。本山納骨を希望する場合、まず現在の菩提寺にその旨を相談し、紹介状や申込手続きを依頼します。遺骨の一部を分骨して納める形が一般的で、受付は随時行われています。費用は志として納める「永代経懇志」が必要で、額は決まっていませんが目安として数万円~が多いようです。本山に納骨すると、そのお寺の永代経法要などで継続的にご供養いただけるため、浄土真宗の信徒にとっては安心感があります。手続きの詳細は各本山の案内ページや菩提寺に確認してください。
Q6: 浄土真宗では葬儀や法事のとき「御冥福をお祈りします」はNGって本当?
A6: 本当です。浄土真宗では亡くなった方はすぐ成仏して極楽浄土へ往くと考えるため、「冥福」(亡者が冥土で幸福になること)を祈る必要がないのです。「ご冥福をお祈りします」は他宗では一般的な弔辞ですが、浄土真宗の場では使わず、「ご愁傷様です」「ご遷化(せんげ)の報に接し…」など教えに沿った表現を用います。マナーとして覚えておきましょう。
まとめ - 浄土真宗でも自分に合った供養の形がきっと見つかる
浄土真宗には永代供養の考え方はないものの、時代のニーズに合わせて現実的な解決策が用意されています。
この記事のポイント
浄土真宗で永代供養ができないのは教義上の理由
それでも実際には永代供養墓を利用する方法が複数ある
菩提寺相談、宗派対応寺院、宗派不問霊園、本山納骨の4つの選択肢
費用や形態は様々なので、比較検討が重要
大切なのは、浄土真宗の教えへの理解を深めつつ、ご自身が安心できる方法を選ぶことです。後継ぎがいない、遠方に住んでいるなどの理由でお墓の将来に不安を感じていても、必ず解決策はあります。
この記事をきっかけに、ぜひ一度ご家族やお寺と話し合ってみてください。きっと納得のいく供養の形が見つかるはずです。無縁墓になる心配をせず、安心して未来を迎えられるよう、今から準備を始めましょう。
この記事のポイント
浄土真宗で永代供養ができないのは教義上の理由
それでも実際には永代供養墓を利用する方法が複数ある
菩提寺相談、宗派対応寺院、宗派不問霊園、本山納骨の4つの選択肢
費用や形態は様々なので、比較検討が重要
大切なのは、浄土真宗の教えへの理解を深めつつ、ご自身が安心できる方法を選ぶことです。後継ぎがいない、遠方に住んでいるなどの理由でお墓の将来に不安を感じていても、必ず解決策はあります。
この記事をきっかけに、ぜひ一度ご家族やお寺と話し合ってみてください。きっと納得のいく供養の形が見つかるはずです。無縁墓になる心配をせず、安心して未来を迎えられるよう、今から準備を始めましょう。