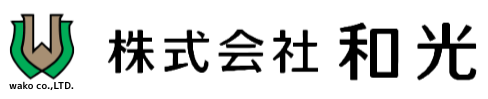通話料無料 9:00~17:30
0120‐66‐4114
永代供養の費用は誰が払う?失敗しない費用分担と安心の備え完全ガイド
投稿日:2025年4月13日

目次
- 永代供養の費用は誰が払うのか【基本知識】
- 継承者(祭祀承継者)が全額を支払う場合
- 家族・親族で費用を分担する場合
- 本人が生前に支払う場合(生前契約)
- 永代供養の費用負担で起こりやすいトラブルと対策
- トラブル事例1:祭祀承継者に任せきりにして他の親族が関与しない
- トラブル事例2:費用の話をあいまいにしたまま先延ばしにした
- トラブル事例3:一部の親族だけで決めてしまった
- 永代供養にかかる費用の内訳と相場
- 永代供養料
- 納骨法要料(お布施)
- 彫刻料(刻字料)
- 管理費(年間費用)
- 永代供養費用の支払い方法とタイミング
- 一般的な支払い方法
- 支払い期間について
- 万が一費用を用意できない時の対処法
- より安価な供養プランの検討
- 公的補助の活用
- メモリアルローンの利用
- 両家墓・合同墓で費用シェア
- まとめ
永代供養の費用は誰が払うべきなのか疑問に思っていませんか?子供に負担をかけたくない、長男だから支払うべき?など様々な悩みが生じるものです。本記事では、永代供養費用の負担者選びから、トラブルを避けるための話し合いのポイント、相場まで詳しく解説します。家族間で揉めずに納得のいく永代供養の準備を進めるための完全ガイドです。
永代供養の費用は誰が払うのか【基本知識】
永代供養の費用を誰が払うかについては、法律上の明確な決まりはありません。従来は長男など家の跡継ぎが支払うという慣習がありましたが、現代では様々なパターンがあります。基本的には祭祀承継者(さいししょうけいしゃ)が負担することが多いですが、家族間の話し合いで決めるのが一般的です。
永代供養の費用を誰が払うべきかは非常にデリケートな問題であり、一概にこうだと断言することは難しいです。ですから、誰が払うべきかを決めるときは、よく話し合うことが大切です。
祭祀承継者とは、お墓や仏壇、位牌などの祭祀財産を受け継ぐ人のことです。民法897条で「慣習に従って決める」とされていますが、これは単なる継承権の話であり、費用負担については明記されていません。つまり、誰が払うべきかは法律ではなく、家族の合意で決めることになります。
永代供養の費用を誰が払うべきかは非常にデリケートな問題であり、一概にこうだと断言することは難しいです。ですから、誰が払うべきかを決めるときは、よく話し合うことが大切です。
祭祀承継者とは、お墓や仏壇、位牌などの祭祀財産を受け継ぐ人のことです。民法897条で「慣習に従って決める」とされていますが、これは単なる継承権の話であり、費用負担については明記されていません。つまり、誰が払うべきかは法律ではなく、家族の合意で決めることになります。
継承者(祭祀承継者)が全額を支払う場合
お墓や仏壇など祭祀財産を引き継いだ人が、その管理責任として費用を負担するケースです。一般的には、故人の子供や孫など直系尊属または直系卑属が祭祀承継者となります。それ以外にも、個人が遺言で指定する場合、家族会議で決定する場合などがあります。
祭祀承継者の決定方法には以下のようなものがあります:
- 故人が遺言で指定した人
- 家族会議で話し合って決めた人
- 慣習に従って長男(または長女)
- 特に決められない場合、家庭裁判所の指定
注意すべき点として、祭祀財産は相続財産とは別のものとして扱われます。つまり、遺産相続を放棄しても、お墓の継承や供養の責任は残ります。祭祀承継者が遺産もすべて相続した場合は、永代供養の費用も全額負担するのが自然でしょう。
祭祀承継者の決定方法には以下のようなものがあります:
- 故人が遺言で指定した人
- 家族会議で話し合って決めた人
- 慣習に従って長男(または長女)
- 特に決められない場合、家庭裁判所の指定
注意すべき点として、祭祀財産は相続財産とは別のものとして扱われます。つまり、遺産相続を放棄しても、お墓の継承や供養の責任は残ります。祭祀承継者が遺産もすべて相続した場合は、永代供養の費用も全額負担するのが自然でしょう。
家族・親族で費用を分担する場合
近年増えているのが、家族や親族で費用を分担するケースです。経済的な事情や、兄弟姉妹が多い場合など、様々な理由で家族や親族で費用を分担する場合があります。分担する割合や方法は、家族間で話し合って決めるのが一般的ですが、遺産を分割して相続したなら、その割合で負担することが多いです。
費用分担の方法としては以下のようなパターンがあります:
- 遺産相続の割合に応じて分担(例:3人兄弟なら3:2:1など)
- 均等に分担(例:4人兄弟なら1/4ずつ)
- 経済状況に応じて分担(余裕のある人が多めに負担)
- 同じお墓に入りたい方同士で分担
家族全員でお墓を守るという考え方に基づき、特定の人に押し付けないことが大切です。みんなで協力することで、後々のトラブルも防ぎやすくなります。
費用分担の方法としては以下のようなパターンがあります:
- 遺産相続の割合に応じて分担(例:3人兄弟なら3:2:1など)
- 均等に分担(例:4人兄弟なら1/4ずつ)
- 経済状況に応じて分担(余裕のある人が多めに負担)
- 同じお墓に入りたい方同士で分担
家族全員でお墓を守るという考え方に基づき、特定の人に押し付けないことが大切です。みんなで協力することで、後々のトラブルも防ぎやすくなります。
本人が生前に支払う場合(生前契約)
終活の一環として、本人が生前に永代供養の費用を支払うケースも増えています。核家族化が進み、お墓の在り方も変わっていく中で、先祖代々のお墓は墓じまいし、子供や孫に負担をかけないよう、永代供養墓を自分で選んで購入するという人も増えてきました。費用を事前に準備できますし、自分が希望する霊園や墓を選べる、費用の計画が立てやすいというメリットがあります。
生前契約のメリットは以下の通りです:
- 子供や家族に費用負担を残さない
- 自分の希望に合ったお墓や供養方法を選べる
- 亡くなった後の家族間のトラブルを防げる
- 相続財産が減り、相続税対策になる場合もある
生前に「寿陵(じゅりょう)」として墓を準備することは、日本の文化では縁起が良いとされてきました。自分のことは自分で責任を持って準備しておくという考え方は、現代社会にも合っていると言えるでしょう。
生前契約のメリットは以下の通りです:
- 子供や家族に費用負担を残さない
- 自分の希望に合ったお墓や供養方法を選べる
- 亡くなった後の家族間のトラブルを防げる
- 相続財産が減り、相続税対策になる場合もある
生前に「寿陵(じゅりょう)」として墓を準備することは、日本の文化では縁起が良いとされてきました。自分のことは自分で責任を持って準備しておくという考え方は、現代社会にも合っていると言えるでしょう。
永代供養の費用負担で起こりやすいトラブルと対策
永代供養の費用負担をめぐってはよくトラブルが発生します。ここでは典型的なトラブル事例とその対策を紹介します。
トラブル事例1:祭祀承継者に任せきりにして他の親族が関与しない
「長男だから」「跡継ぎだから」という理由だけで、一人に費用や手続きをすべて押し付けることで、不満が生じるケースです。
対策:
家族全員で協力体制を整えましょう。お墓は家族みんなのものという認識を持ち、継承者だけに任せずに、できることは分担します。費用だけでなく、手続きや準備も協力して行えば、負担感が減り、家族の絆も深まります。
対策:
家族全員で協力体制を整えましょう。お墓は家族みんなのものという認識を持ち、継承者だけに任せずに、できることは分担します。費用だけでなく、手続きや準備も協力して行えば、負担感が減り、家族の絆も深まります。
トラブル事例2:費用の話をあいまいにしたまま先延ばしにした
「お金の話は後で」と具体的な費用分担を決めないまま進めたことで、後から「こんなに高いとは知らなかった」「なぜ自分が払わなければならないのか」といったトラブルになるケースです。
対策:
早い段階で費用の総額と分担方法について話し合いましょう。誰がいくら負担するか、いつまでに支払うかなど、具体的な金額と期日を決め、可能であれば書面に残しておくとよいでしょう。お金の話はしづらいものですが、後のトラブルを防ぐためにも、曖昧にせず明確にすることが大切です。
対策:
早い段階で費用の総額と分担方法について話し合いましょう。誰がいくら負担するか、いつまでに支払うかなど、具体的な金額と期日を決め、可能であれば書面に残しておくとよいでしょう。お金の話はしづらいものですが、後のトラブルを防ぐためにも、曖昧にせず明確にすることが大切です。
トラブル事例3:一部の親族だけで決めてしまった
「一部の親族だけで話し合って決めた」「連絡がなく知らなかった」などの理由で、後から不満や反発が生まれるケースです。
対策:
関係する親族全員に情報を共有し、意見を聞く場を設けましょう。遠方に住んでいる親族には電話やオンラインでの参加も検討してください。全員が合意形成に関わることで、「聞いていない」「知らなかった」というトラブルを防げます。話し合いは強制ではありませんが、機会を設けることが重要です。
費用負担の話は確かにしづらいものですが、だからこそ早めに話し合うことで後々の揉め事を防げます。少し勇気を出して話し合うことで、家族の絆を守ることができるでしょう。
対策:
関係する親族全員に情報を共有し、意見を聞く場を設けましょう。遠方に住んでいる親族には電話やオンラインでの参加も検討してください。全員が合意形成に関わることで、「聞いていない」「知らなかった」というトラブルを防げます。話し合いは強制ではありませんが、機会を設けることが重要です。
費用負担の話は確かにしづらいものですが、だからこそ早めに話し合うことで後々の揉め事を防げます。少し勇気を出して話し合うことで、家族の絆を守ることができるでしょう。
永代供養にかかる費用の内訳と相場
永代供養にはどのような費用がかかり、いくらくらいが相場なのかを知っておくことも重要です。ここでは主な費用項目と相場を解説します。
永代供養料
永代供養料は、寺院や霊園に永代にわたって遺骨を供養・管理してもらうための基本料金です。お墓の種類によって費用相場が大きく異なります。
| 種類 | 費用相場 | 特徴 |
|---|---|---|
| 合祀墓(ごうしぼ) | 5万円~30万円 | 他の遺骨と一緒に合祀され、最も安価 |
| 集合墓 | 20万円~50万円 | 個別スペースに納骨されるが、期間後に合祀 |
| 樹木葬 | 20万円~150万円 | 自然に囲まれた環境で供養、個別・合祀型あり |
| 個別墓 | 40万円~150万円 | 従来型の墓石があり、一定期間後に合祀 |
| 納骨堂 | 50万円~200万円 | 屋内施設で管理、立地やタイプで費用差が大きい |
一般的なお墓を建てるには、およそ200万円程度がかかりますが、永代供養墓は10万円~150万円程度。最も安い合祀タイプであれば10〜20万円程度となります。
永代供養は一般的なお墓より費用が抑えられる傾向にあり、特に合祀型は費用を大幅に抑えることができます。ただし安価な分、他のご遺骨と混ざり、後から取り出せなくなるなどの制約もあります。
永代供養は一般的なお墓より費用が抑えられる傾向にあり、特に合祀型は費用を大幅に抑えることができます。ただし安価な分、他のご遺骨と混ざり、後から取り出せなくなるなどの制約もあります。
納骨法要料(お布施)
納骨の際に僧侶に読経してもらうためのお礼として、お布施を渡すのが一般的です。
- 納骨法要のお布施相場:3万円~5万円程度
- 永代供養料に含まれている場合もあるので確認が必要
納骨法要以外にも、年忌法要などを執り行う場合には別途お布施が必要になることがあります。永代供養では一般的なお墓よりも法要の回数が少ないケースが多いため、長期的には費用抑制になります。
- 納骨法要のお布施相場:3万円~5万円程度
- 永代供養料に含まれている場合もあるので確認が必要
納骨法要以外にも、年忌法要などを執り行う場合には別途お布施が必要になることがあります。永代供養では一般的なお墓よりも法要の回数が少ないケースが多いため、長期的には費用抑制になります。
彫刻料(刻字料)
墓誌やプレートに故人の名前や戒名を彫刻する費用です。
- 彫刻料の相場:3万円~5万円程度
- 文字数や素材によって費用が変わる場合がある
永代供養墓では墓石を建てないタイプもありますが、その場合でも小さなプレートなどに名前を刻むケースが多く、その際に彫刻料が発生します。
- 彫刻料の相場:3万円~5万円程度
- 文字数や素材によって費用が変わる場合がある
永代供養墓では墓石を建てないタイプもありますが、その場合でも小さなプレートなどに名前を刻むケースが多く、その際に彫刻料が発生します。
管理費(年間費用)
管理費はお墓の種類や収骨人数によって異なり、費用相場は、毎年支払うケースでは年間5,000円〜2万円ほどです。毎年ではなく契約時にまとめて支払える場合もあります。その場合は、個別に安置される期間の年数分の管理費を支払います。17回忌までの契約なら17年分、33回忌までの契約なら33年分、という具合に支払うことになるでしょう。
多くの永代供養墓では、契約時に永代供養料として一括で支払うことで、その後の年間管理費は不要としているところが多いですが、施設によって対応が異なるため、契約前に確認が必要です。
合祀型の永代供養墓では、年間管理費がかからないケースがほとんどです。個別に管理するタイプでは、一定期間(13回忌や33回忌まで)の管理費が必要になることがあります。
多くの永代供養墓では、契約時に永代供養料として一括で支払うことで、その後の年間管理費は不要としているところが多いですが、施設によって対応が異なるため、契約前に確認が必要です。
合祀型の永代供養墓では、年間管理費がかからないケースがほとんどです。個別に管理するタイプでは、一定期間(13回忌や33回忌まで)の管理費が必要になることがあります。
永代供養費用の支払い方法とタイミング
永代供養の費用はどのように支払い、いつまで払い続けるのかについても理解しておきましょう。
一般的な支払い方法
永代供養の費用は、基本的に契約時に一括で支払うケースが多いです。寺院や霊園によって対応は異なりますが、以下のような支払い方法があります:
- 現金一括払い:契約時にその場で現金支払い(多くの寺院で一般的)
- 銀行振込:指定口座への振込(事前確認が必要)
- クレジットカード:一部の施設では対応している場合もある
- 分割払い:メモリアルローンなどの提携ローンを利用できる場合もある
特に高額な永代供養墓を選んだ場合は、一括払いが難しいケースもあるでしょう。そのような場合は、分割払いができるか確認するとよいでしょう。葬儀社や石材店が提携金融機関のローン(メモリアルローン)を用意していることもあります。
- 現金一括払い:契約時にその場で現金支払い(多くの寺院で一般的)
- 銀行振込:指定口座への振込(事前確認が必要)
- クレジットカード:一部の施設では対応している場合もある
- 分割払い:メモリアルローンなどの提携ローンを利用できる場合もある
特に高額な永代供養墓を選んだ場合は、一括払いが難しいケースもあるでしょう。そのような場合は、分割払いができるか確認するとよいでしょう。葬儀社や石材店が提携金融機関のローン(メモリアルローン)を用意していることもあります。
支払い期間について
永代供養の費用を支払う期間は、寺院・霊園によって違いがあります。契約するときに、永代供養料や諸費用をすべて一括して支払うパターンです。合祀墓はこのパターンが多く、管理費も含まれていますので、その後の支払いが発生しません。個別墓に納骨した場合は、永代供養料にプラスして、個別の安置期間中の管理費が発生することがあります。
支払い期間のパターンとしては、主に以下のようなものがあります:
1. 一括払いのみ(追加費用なし):契約時に支払った後は一切費用がかからないタイプ。合祀墓に多い。
2. 個別安置期間中のみ管理費が必要:個別で管理される期間(13回忌や33回忌まで)は管理費が必要で、合祀後は不要になるタイプ。
3. 承継者がいる限り管理費が必要:承継者がいて支払い続ける限り個別管理され、支払いが滞ると合祀されるタイプ。
4. 生前契約は納骨までのみ管理費が必要:永代供養墓を生前契約した場合、実際に納骨するまでの間は管理費が発生することがあります。契約者が亡くなり、納骨されれば、管理費が不要となるケースです。
契約前に、「いつまで払い続けるのか」を必ず確認し、将来的な負担についても考慮することが大切です。
支払い期間のパターンとしては、主に以下のようなものがあります:
1. 一括払いのみ(追加費用なし):契約時に支払った後は一切費用がかからないタイプ。合祀墓に多い。
2. 個別安置期間中のみ管理費が必要:個別で管理される期間(13回忌や33回忌まで)は管理費が必要で、合祀後は不要になるタイプ。
3. 承継者がいる限り管理費が必要:承継者がいて支払い続ける限り個別管理され、支払いが滞ると合祀されるタイプ。
4. 生前契約は納骨までのみ管理費が必要:永代供養墓を生前契約した場合、実際に納骨するまでの間は管理費が発生することがあります。契約者が亡くなり、納骨されれば、管理費が不要となるケースです。
契約前に、「いつまで払い続けるのか」を必ず確認し、将来的な負担についても考慮することが大切です。
万が一費用を用意できない時の対処法
経済的な事情で永代供養の費用負担が難しい場合の対処法についても見ていきましょう。
より安価な供養プランの検討
費用が厳しい場合は、より安価な永代供養の形態を検討することができます。
- 合祀型を選ぶ:個別管理より合祀型のほうが大幅に費用を抑えられます。合祀墓は5万円~15万円程度から選べるケースもあります。
- 公営の合葬墓を利用する:自治体が運営する合葬墓は、民営に比べて安価な場合が多いです。
- 特別な装飾やサービスを省く:彫刻やオプションサービスを最小限にすることで費用を抑えられます。
ただし、合祀型は一度納骨すると取り出せなくなる等の制約があるため、費用面だけでなく供養方法についても十分理解した上で選ぶことが重要です。
- 合祀型を選ぶ:個別管理より合祀型のほうが大幅に費用を抑えられます。合祀墓は5万円~15万円程度から選べるケースもあります。
- 公営の合葬墓を利用する:自治体が運営する合葬墓は、民営に比べて安価な場合が多いです。
- 特別な装飾やサービスを省く:彫刻やオプションサービスを最小限にすることで費用を抑えられます。
ただし、合祀型は一度納骨すると取り出せなくなる等の制約があるため、費用面だけでなく供養方法についても十分理解した上で選ぶことが重要です。
公的補助の活用
自治体によっては、墓じまいや改葬に関する補助金制度を設けている場合があります。
- 墓石撤去費用の一部補助
- 無縁墓の整理に関する支援
- 高齢者・生活困窮者向けの葬祭扶助
永代供養自体への直接補助は少ないですが、墓じまいとセットで永代供養を検討している場合は、自治体の担当窓口に相談してみるとよいでしょう。「お墓がある自治体の役所に問い合わせる」のが基本です。
- 墓石撤去費用の一部補助
- 無縁墓の整理に関する支援
- 高齢者・生活困窮者向けの葬祭扶助
永代供養自体への直接補助は少ないですが、墓じまいとセットで永代供養を検討している場合は、自治体の担当窓口に相談してみるとよいでしょう。「お墓がある自治体の役所に問い合わせる」のが基本です。
メモリアルローンの利用
まとまった費用が用意できない場合は、専門のローンを利用する方法もあります。
- 葬祭ローン(メモリアルローン):葬儀・墓石・永代供養などに使える専用ローン
- 金利は一般的な消費者ローンより低いケースが多い
- 地方銀行やJA、生協などに相談するとよい
返済計画をしっかり立てた上で利用することが大切です。高齢者の場合は審査が通りにくいこともあるため、必要に応じて保証人を立てるなどの対策も考慮しましょう。
- 葬祭ローン(メモリアルローン):葬儀・墓石・永代供養などに使える専用ローン
- 金利は一般的な消費者ローンより低いケースが多い
- 地方銀行やJA、生協などに相談するとよい
返済計画をしっかり立てた上で利用することが大切です。高齢者の場合は審査が通りにくいこともあるため、必要に応じて保証人を立てるなどの対策も考慮しましょう。
両家墓・合同墓で費用シェア
配偶者側と自分側の実家で一つのお墓を共有する「両家墓」という選択肢もあります。
- 費用を折半できるため経済的負担が減る
- 「お墓の承継者がいない」という問題の解決にもなる
- 霊園や寺院によって受け入れ条件が異なる場合もある(宗派など)
柔軟な発想で供養の形を考えることで、費用面の課題を解決できる場合もあります。
- 費用を折半できるため経済的負担が減る
- 「お墓の承継者がいない」という問題の解決にもなる
- 霊園や寺院によって受け入れ条件が異なる場合もある(宗派など)
柔軟な発想で供養の形を考えることで、費用面の課題を解決できる場合もあります。
まとめ
永代供養の費用は誰が払うべきか、明確な決まりはありません。かつては長男や跡継ぎが負担するのが一般的でしたが、現代では家族で分担したり、本人が生前に支払ったりするケースも増えています。最も大切なのは、家族でよく話し合い、全員が納得できる形で決めることです。
費用の相場は永代供養の種類によって大きく異なり、合祀墓なら5万円程度から、個別墓なら100万円を超える場合もあります。将来の管理費についても事前に確認し、家族の負担にならない選択をすることが重要です。
費用負担で揉めないようにするには、話し合いを先送りにせず、具体的な金額と分担方法を早めに決め、可能であれば書面に残しておくことをおすすめします。特定の人に負担を押し付けず、みんなで支え合う姿勢が大切です。
永代供養は、亡き人を大切に弔い、残された家族も安心できる供養方法です。負担を一人にせず分かち合うことが、故人への何よりの供養になるでしょう。本記事を参考に、ご家族で納得のいく永代供養の準備を進めてください。
費用の相場は永代供養の種類によって大きく異なり、合祀墓なら5万円程度から、個別墓なら100万円を超える場合もあります。将来の管理費についても事前に確認し、家族の負担にならない選択をすることが重要です。
費用負担で揉めないようにするには、話し合いを先送りにせず、具体的な金額と分担方法を早めに決め、可能であれば書面に残しておくことをおすすめします。特定の人に負担を押し付けず、みんなで支え合う姿勢が大切です。
永代供養は、亡き人を大切に弔い、残された家族も安心できる供養方法です。負担を一人にせず分かち合うことが、故人への何よりの供養になるでしょう。本記事を参考に、ご家族で納得のいく永代供養の準備を進めてください。